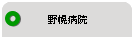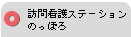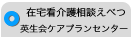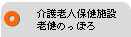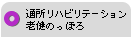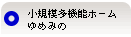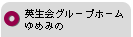小規模多機能型居宅介護とは?
小規模多機能型居宅介護は、「通い(デイサービス)」を中心に、利用者の様態や希望などに応じて、随時「訪問(ヘルパー)」や「宿泊(ショートステイ)」を組み合わせてサービスを提供し、住み慣れた地域や自宅での生活が継続出来るように支援致します。
この「通い」「訪問」「宿泊」のサービスは、一つの事業所で同じ職員のもと行われるため、「通いなれた」「見慣れた」という馴染みの関係が築きやすく、利用される方・特に認知症の方にとっては、大きな安心感につながります。
そのため、これまでデイサービスとショートステイを別々の事業所で利用した時に、起こりがちだった、環境の変化による混乱等が回避されやすくなります。
利用される方や家族の状態や状況、ご希望に応じて柔軟にその時必要なサービスを利用できる。それが小規模多機能型居宅介護です。
小規模多機能型居宅介護のメリット
- 「通い」「訪問」「宿泊」どのサービスを利用しても、いつも顔馴染みのスタッフがケアを行います。
- 25名の登録制で、「通い」の1日利用定員は15名と少人数なため、家庭的な雰囲気の中で、他の利用者や職員と楽しく過ごすことが出来ます。
- 年中無休なので、いざという時にも対応可能です。
- 月額定額制のため、介護保険区分支給限度額からは、はみだす心配がありません。(他サービス利用の場合を除く)
- 認知症介護実践者研修等を修了したスタッフが配置されているので、認知症の方の受け入れも安心です。
- 「通い」サービスの提供時間や送迎時間も柔軟に対応いたします。
- 柔軟に「宿泊」のご利用が可能です。今、「宿泊」の必要がない方でも、将来的に安心です。
- 「通い」「訪問」「宿泊」のサービスを柔軟に組み合わせることにより、家族の介護負担の軽減が図れます。
小規模多機能型居宅介護の誕生
小規模多機能型居宅介護は、平成18年(2006年)4月の介護保険制度改正により制度化され誕生しました。
現在、急速に高齢化が進む日本では、施設中心の介護体制では対応できなくなることは明白でした。厚生労働省は、今後の介護の在り方として、「施設」から「在宅」への転換する方針を打ち出しました。
そこで、新しく創設されたのが、小規模多機能型居宅介護です。小規模多機能型居宅介護は、地域で要介護者を支えるコミュニティとして、大きな役割を担うことになりました。
小規模多機能型居宅介護の前身
介護保険制度で制度化される以前、小規模多機能型居宅介護は「宅老所」という名称などで、存在していました。この「宅老所」は、大きな規模の老人施設とは違い、介護や支援を必要としている高齢者に民家等でサービスを提供することにより、気の知れた仲間同士と家庭的な環境の下で過ごすことができるというものでした。大規模老人施設の整備が進む中、一方では理想的な介護の在り方である「宅老所」での個別ケア等の実践を取り入れる事業所が増えていきました。
介護や支援が必要な高齢者にとって、馴染みの関係や信頼関係が構築しやすい、この小規模の「宅老所」は理想的な形態でした。特に要介護者の半数を占めるといわれる認知症高齢者にとっては、住み慣れた地域で、出来る限り環境を変えずに介護ケアサービスを受けることができるという事が大切なのです。
昔は、家族や隣近所で支えあってきた高齢者の介護も、現在では核家族化が進み、ご近所付き合いも少なくなっています。そんな良き時代を再現すべく、地域ケア・コミュニティの拠点として小規模多機能型居宅介護が誕生し注目されています。